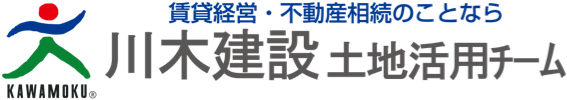お金がかからない土地活用とは?低予算でも出来る事例を紹介
はじめに
「土地を持っているけれどお金がない!」
「低予算でも出来る土地活用ってないの?」
と、お悩みではありませんか?
特に近年は、土地の価格変動や空き家放置法の制定等で「放置する」ことがかえって大きな損失につながるケースも増えています。
「土地活用」と聞くと「莫大な資金が必要」「自分には無理」と感じてしまいがちです。
そんなお悩みを解決する初期費用をほとんどかけずに土地を活かす方法があります。資金に余裕がない方でもお持ちの土地を活用出来る可能性があります。
この記事では具体的な活用手法と事例、失敗しないためのポイントまで、わかりやすく解説していきます。「土地の使い道がわからない」「リスクが怖い」と感じている方も、まずは気軽に読んでください。あなたの土地にぴったりの活用方法を見つける参考になります。
目次
1-1 )低予算の土地活用が求められる背景
1-2 )固定資産税等の出費の対策
1-3 )手放したくない土地を維持する施策として
2 )お金をかけない土地活用とは?
2-1 )立地・需要に合った活用方法を選ぶ
2-2 )長期的な視野で活用計画を立てる
2-3 )出資者がいる事業を選ぶ
3 )お金をかけない土地活用の方法
3-1 )一般定期借地権を利用した土地活用
3-2 )最低限の農業を行って農地を維持する
3-3 )建設協力金方式でテナント運用する
3-4 )等価交換方式で賃貸を建設
4 )お金のかからない土地活用事例
4-1 )駐車場経営
4-2 )貸倉庫運営
4-3 )太陽光発電
4-4 )貸農園
4-5 )貸店舗用地
4-6 )野立て看板
5 )失敗しないために注意すべきポイント
5-1 )契約内容をチェック
5-2 )近隣とのトラブルリスクを把握する
5-3 )税金・維持費を見落とさない
6 )お金をかけない土地活用を成功させるために
6-1 )まずは専門家に相談してみよう
6-2 )小さな一歩から始めるのが成功のコツ
6-3 )定期的に土地の活用状況を見直そう
7 )まとめ
1 )低予算で土地活用するメリットとは

土地を所有していると、何もしなくても管理の手間や費用がかかります。
土地を持ち続けること自体が負担になることもあり、悩んでいる方も少なくありません。
そこで注目されているのが低予算で行う土地活用です。
ここではなぜ「低予算の土地活用」が求められているのか、そしてそれによって得られるメリットについて整理していきます。
1-1 )低予算の土地活用が求められる背景
近年、団塊の世代が高齢化を迎え不動産を相続するケースが増えています。一方で、人口は減少傾向にあり、土地や家を売りたくてもなかなか買い手がつかない状況も珍しくありません。
このため、空き家問題や放置された土地の管理トラブルが全国で深刻化しています。
- 固定資産税などの税金を払い続ける
- 建物の倒壊事故等の責任
- 荒廃した場合、近隣住民とのトラブル
「売れないから持っているしかない」「でも持っていると税金や管理費がかかる」
というジレンマを抱える中で
「できるだけコストをかけずに土地を活用したい」というニーズが高まっています。
1-2 )固定資産税等の出費の対策
土地や不動産を所有していると固定資産税や都市計画税が発生します。
さらに、相続税や維持管理費もかかるため、何もせずに放置しているとただ出費が増え続けるだけになってしまいます。
不動産は「持っていれば安心」という時代ではなくなりました。売却するか運用して収益を上げなければ出費だけを作り出す負の資産という状況です。
そこで初期投資を抑えながら不動産でお金を得る方法が必要になります。出費分をカバーし、場合によってはプラスの収益を得ることで不動産を負の資産にならない対策を取ることができます。
1-3 )手放したくない土地を維持する施策として
遺産などで親の土地を相続した際、「思い出のある土地だから売りたくない」「将来のために残しておきたい」という気持ちを持つ方も多いでしょう。
しかし、土地を持ち続けるということは固定資産税や管理の手間は避けられません。
また、「自分で手入れをする時間もなかなか取れない」「費用もかけられない」という悩みも出てきます。
こうした問題を解決する方法の1つがお金と手間をあまりかけずにできる土地活用です。
うまく活用することで、土地を手放すことなく負担を減らし、大切な資産を次の世代へとつないでいくことが可能になります。
2 )お金をかけない土地活用とは?
「お金をかけない土地活用」は初期費用を抑えて手軽に始められる魅力があります。しかし、選び方や管理方法を誤ると思わぬトラブルや損失を招くリスクもあるので注意が必要です。
ここでは、失敗を防ぎながら土地を賢く活用するために押さえておきたい3つの重要なポイントについて解説します。
2-1 )立地・需要に合った活用方法を選ぶ
もっとも基本的なことですが、土地活用はその土地に適した方法を選ぶことが大切です。
特に低予算で事業を行う場合は立地や広さ、地域などの特性を活かすことがカギとなります。
例えば、立地的に不利な場所で事業を行おうとすれば、競合と差をつけるための設備投資や広告宣伝費、思ったような利益が上がらない場合などのリスクも抱えることになります。
- 設備等の追加費用がかかる
- 事業費用が大きくなりやすい
- 集客が難しい
- 想定していた利益を得られない可能性が高くなる
- 借り手や買い手が見つかりにくくなる
このようなリスクを避けるために、「土地の広さ」「周辺環境」「交通アクセス」「人口動態」などを総合的に見て、「この立地ならどんなニーズがあるか」を調査しながら活用方法を検討しましょう。
2-2 )長期的な視野で活用計画を立てる
土地活用の際に短期的な利益だけに目を向けると後から思わぬ問題に直面することがあります。特に土地活用は一度始めると長期間にわたることが多くなります。長期的な視野で計画を立てることが大切です。
例えば、初期費用がかからない方法を選んでも、運用開始後に維持費や管理費が予想以上にかかることがあります。さらに、周囲の環境の変化や法規制の変更などによって、収益性が低下するリスクもあります。
「どんな時期に、どんな対応が必要になるか」を知り、長期的な視野で計画を行います。
土地活用を行う際には、3年後、5年後、10年後を見据えたプランを考え、その都度見直しを行うようにしましょう。
予期せぬ変化に柔軟に対応し、安定した収益を維持することができます。
2-3 )出資者がいる事業を選ぶ
お金をかけずに土地活用をするもっともわかりやすい方法として、自分で資金を用意しなくて済む方法を選ぶことが大切です。
そこで注目したいのが、「出資者がいる事業を選ぶ」という考え方です。
次の章で解説しますが、出資者がいる事業で土地活用する方法として次のような方法が挙げられます。
- 定期借地権を利用した土地活用
- 事業用借地権で土地を貸し出す
- 建設協力金方式でテナント運用する
- 等価交換方式で賃貸を建設
これらの手法を活用すれば、オーナー自身が大きな初期投資をせずに土地活用をスタートできるのがメリットです。
土地を手放すことなく、資金面の負担を抑えて運用していきたいなら、「出資者がいる事業を選ぶ」ことは有効な選択肢といえるでしょう。
ただし、出資者の意向を無視できないという側面もあります。
契約内容によっては貸し出し期間中の土地の使い方や再利用に制限がかかる場合もあるため、慎重な交渉と事前確認が必要です。
詳しくは次の章で確認していきましょう。
3 )お金をかけない土地活用の方法

お金をかけずに始められる代表的な土地活用の方法として4つの手法をご紹介します。それぞれの内容やメリット・デメリット、活用例なども含めて解説していきます。
3-1 )一般定期借地権を利用した土地活用
一般定期借地権とは
50年以上の一定期間土地を貸し出し、契約終了後に更地にして返してもらう契約方式です。
地主が土地を貸す場合昔の法律では借主が優遇されていたため、実質貸した土地が返ってこないという問題点がありました。現在の法律では契約期間を過ぎたら継続はせず。土地も更地にして戻すことが定められています。
利用方法に制限がなく、個人の住宅などさまざまな用途で貸し出すことができます。
この方法で土地を貸すことで、土地のオーナーは土地を所有し続けながら、安定した賃料収入を得ることができます。
- 土地を手放すことなく収益化できる
- 契約終了後には更地で土地を取り戻せる
- 固定資産税などの維持コストを地代で賄いやすい
- 契約期間中は自分で自由に使うことができない
- 需要がないエリアでは借り手が見つかりにくい
- 契約内容によってはトラブルが発生するリスクもある
こんな人におすすめ
将来的に土地を自分たちのために残したいが、当面の間は活用したいという方に適しています。長期的な利用となるため周辺の需要をきちんと調査したうえで賃料や契約条件を細かく取り決めておきましょう。
3-2 )最低限の農業を行って農地を維持する
事業用定期借地権とは
10年以上50年未満の一定期間、店舗やオフィス、工場などの事業を目的として土地を貸し出す契約方式です。一般定期借地権同様に契約期間終了時には借主が更地に戻して返却されます。
一般定期借地と異なり「事業用」として利用する制限があります。事業用定期借地権は一般定期借地権より短い契約期間にできることや、高い賃料を得やすいなどの特徴があります。
- 比較的短い期間でも活用が可能
- 建設費が不要で安定収益を得られる
- 相手側が事業展開するため地主のリスクは低め
- 借主の事業が失敗すると収益が途絶えるリスクがある
- 立地条件によっては借り手が限定される
- 契約内容が不十分だと問題が起きやすい
こんな人におすすめ
ロードサイドや商業地、駅近など、事業ニーズが高いエリアの土地を持つ方に向いています。一方で、契約書をきちんと作成して借主の信用調査も怠らないことがトラブル防止のために不可欠です。
3-3 )建設協力金方式でテナント運用する
建設協力金方式とは
テナント企業がテナントの建築費用の一部または全額を先に支払い、その後賃料の一部から差し引きます。簡単に言うと、テナント企業が建築費用を立て替えます。オーナーはその建築費用を月々の賃料の一部から立て替えてもらったお金と相殺していくという方法です。
これによって賃料は安くなってしまいますが、オーナーは資金なし、またはほとんどお金を使わずにテナント経営を行うことができます。
事業用定期借地と大きく異なるのが、建物が残るということです。
- 資金提供できるテナントを確保できること
- 立地に十分なテナント需要があること
- 長期にわたる賃貸契約を結べること
- 自己資金ゼロで建物を建てられる
- 建物が資産として手元に残る
- 賃料収入が安定的に入る
- 契約終了後更地に戻すのに費用が必要
- 建物仕様にテナントの要望が反映されることが多い
- 将来の空室リスクを想定しておく必要がある
こんな人におすすめ
好立地に土地を持ち、信頼できるテナント候補がいる方に向いています。ただし、テナントに強く依存する形になるため、万一の撤退リスクや建物の仕様、管理責任については慎重に検討しておく必要があります。
3-4 )等価交換方式で賃貸を建設
等価交換方式とは
自分が所有している土地を不動産会社に提供し、その代わりに完成した建物の一部を受け取る方法です。
例えば、マンションや商業ビルの建設を希望する不動産会社と契約するとします。土地の提供と引き換えに完成後のマンションの数室や店舗区画などを元の土地代と同等分の「区分所有権」として取得します。
オーナー側は、建築費用や開発費用などの初期費用を負担する必要がないため、自己資金を使わずに収益物件を手に入れられる点が大きな特徴です。具体的には、不動産会社と交渉して土地の価値に応じた建物の一部を受け取り、その後、それを賃貸に出して家賃収入を得るといった形で活用されます。
ただし、土地の一部を手放すことになるため、将来的な相続や売却を考えている場合には慎重な検討が必要です。また、建物の完成後に得られる権利の割合や位置、用途などについても、事前にしっかりと契約内容を確認しておくことが大切です。
- 自己資金を出さずに賃貸物件を所有できる
- 土地を売却せずに活用できる
- 家賃収入を得ながら資産を維持できる
- 対象となる土地が限定される
- 建物の管理費や修繕費が将来的に発生する
- 契約内容が複雑になりやすい
こんな人におすすめ
広い土地を持ち、資産として残したいと考える方に非常に向いています。ただし、土地の一部を手放すことになるため、将来的な相続や売却を考えている場合には慎重な検討が必要です。また、建物の完成後に得られる権利の割合や位置、用途などについても事前にしっかりと契約内容を確認しておくことが大切です。
4 )お金のかからない土地活用事例

ここでは、実際に「初期費用を抑えて取り組める土地活用」の代表的な事例を紹介します。3章で紹介した活用方法とも関連付けながら、それぞれの特徴を見ていきましょう。
4-1 )駐車場経営
駐車場経営の特徴
空き地をそのまま、あるいは整地して砂利を敷いたり、アスファルト舗装を施したりすることで、車を停めるスペースとして貸し出す土地活用の方法です。運営形態には、契約者が月ごとに利用する「月極駐車場」や、時間単位で利用できる「コインパーキング(時間貸し)」などがあります。
コインパーキングとして運用する場合には機械設備の設置が必要となるため、ある程度の初期費用がかかることがあります。ただし、これらの設備は運営会社が負担してくれる場合もあるため、契約内容をよく確認することが大切です。
駅に近い場所や住宅密集地、商業施設周辺などでは需要が高い一方で、競争のある地域では、屋根付きのカーポートや防犯カメラの設置といった差別化のための工夫も求められる場合があります。
- 比較的少ない初期投資で始められる
- 需要があれば安定した収益が見込める
- 解約・転用がしやすく、土地の流動性が高い
- 場所によっては利用者が集まらないリスクがある
- 舗装や管理に一定の費用がかかる
- 収益性はそれほど高くない場合がある
こんな人におすすめ
定期借地権や事業用借地権ほど大規模な契約に踏み切れない場合や、とりあえず手軽に土地活用を始めたい方に向いています。ただし、立地による収益差が大きいため事前の市場調査が必要です。
4-2 )貸倉庫運営
貸倉庫運営の特徴
プレハブ式の簡易倉庫やコンテナ倉庫を設置し、それを個人や企業に貸し出す土地活用の方法です。住宅地周辺や物流エリアでは「貸しコンテナ」や「トランクルーム」といった形態の倉庫需要が高まりつつあります。
土地の整地さえできていれば、建築確認が不要な簡易構造の倉庫を設置することが可能で、初期費用を抑えながら始められるのが魅力です。特に小規模な土地や、住宅地に近い場所などで有効に活用できるケースが多く見られます。
また、倉庫として貸すことで人の出入りが少なく近隣トラブルも起こりにくいため、静かな土地活用法としても注目されています。
- 住宅地以外でも需要が見込める
- 初期コストを抑えた簡易な倉庫設置が可能
- 管理が比較的楽で、手間がかかりにくい
- 設置費用が一定程度必要
- 空室リスクがある
- 盗難や事故などのリスク対策も必要
こんな人におすすめ
事業用借地権や建設協力金方式と同様、「事業向けニーズ」を生かした土地活用です。工業地域や幹線道路沿いなど、住宅地以外の土地を活用したい方に適しています。
4-3 )太陽光発電
太陽光発電の特徴
土地に太陽光パネルを設置し、太陽のエネルギーから電気を生み出して、それを電力会社に売ることで収益を得る活用方法です。広い土地が必要になりますが、人や車が出入りしにくい土地でも活用できるのが大きな特徴です。
設置には初期費用がかかりますが、条件によっては国や自治体の補助金や優遇制度を利用できることがあります。また、売電価格は契約時の条件で一定期間固定されるため、収益の見通しを立てやすい特徴もあります。
環境貢献にもつながることから、低予算での土地活用方法として根強い人気があります。
- 運用開始後は手間がほとんどかからない
- エコ事業としてイメージアップにつながる
- 国の固定価格買取制度(FIT制度)を利用できる場合がある
- 初期設置コストがやや高い
- 売電価格の下落リスクがある
- 自然災害による設備破損リスクもある
こんな人におすすめ
山林や田畑など、活用しにくい広い土地が向いています。少ない利益でも広い土地に手間をかけずに活用していきたい人におすすめです。補助金や売電価格の制度は度々変更されることがあります。制度の変化には注意をしましょう。
4-4 )貸農園
貸農園の特徴
貸農園は土地を小さな区画に分けて個人や団体に貸し出し、家庭菜園や趣味の農作業に利用してもらう土地活用の方法です。初期費用が比較的少なく、整地や簡単な設備を整えるだけで始められる点が魅力です。近年は健康志向の高まりや農業体験への関心が高く、特に都市部を中心にニーズが拡大しています。地域住民との交流を促す効果もあり、空き地を活かしながら地域貢献にもつながる手法として注目されています。
- 未利用地でも有効活用できる
- 管理が比較的シンプル
- 地域活性化にもつながりやすい
- 利用者の確保が必要
- 農作業によるトラブル(ゴミ問題など)が起きることもある
- 収益性はそれほど高くない
こんな人におすすめ
農業を続けられなくなった広い田畑を相続した人におすすめです。農地は使い道に制限があるため、無理に処分せず活用したい人に向いています。貸す際は農地法の手続きが必要になる点に注意しましょう。
4-5 )貸店舗用地
貸店舗用地の特徴
土地を店舗や飲食店などの事業者に貸し出す方法です。通常。建物は借主が建設し土地だけを貸す形になります。この方法では事業用定期借地権や一般定期借地権などを利用し、初期費用をかけずに安定した収入を得ることができます。ただし、借主が事業を失敗した場合のリスクもあります。また、地域の商業環境や需要を十分に調査することが大切です。
- 初期費用をかけずに安定収益が期待できる
- 好立地であれば高額な地代収入が得られる
- 長期契約が見込める
- 立地に左右されるため競争が激しい
- 借主の撤退リスクがある
- 契約終了時の原状回復などトラブルになる場合もある
こんな人におすすめ
都市部やロードサイドの立地に強みを持つ人に適しています。安定した収益を得るチャンスが大きい反面、相手企業の経営状況にも注意を払う必要があります。
4-6 )野立て看板
野立て看板の特徴
道路沿いや人目につく場所に看板スペースを設置し、広告主に貸し出す方法です。土地が小規模でも利用でき、初期投資が少なくて済むため、比較的低コストで始められます。ただし、周囲の視認性や交通量をよく調査し、広告需要が高いエリアを選ぶことが重要です。
- 設置コストが比較的安価
- 小面積の土地でも収益化できる
- 手間が少なく安定的な副収入になる
- 利益はかなり少なめ
- 景観条例や建築基準法の規制を受ける場合がある
- 契約終了後の撤去費用が発生することもある
こんな人におすすめ
大規模契約が難しい小さな土地、交通量の多い道路沿いを持っている方に向いています。手軽な副収入源として人気ですが、設置や運用に際して法律規制に注意が必要です。
5 )失敗しないために注意すべきポイント

お金をかけずに土地活用を始める場合でも、適当に進めると失敗するリスクがあります。ここでは、成功に近づくために押さえておきたい重要なポイントを紹介します。
5-1 )契約内容をチェック
土地活用を行う際、貸し出しや建設に関する契約を結ぶことがほとんどです。
このとき、契約書の内容を十分に理解しないままサインしてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。
特に「定期借地権」や「事業用借地権」「建設協力金方式」などは、契約の期間や更新、建物の所有権、返還時の条件などが細かく定められています。
例えば、契約満了後に建物をどうするか(解体費用は誰が負担するのか)など、重要なポイントが抜けていると、思わぬ費用負担が発生するリスクもあります。
わからない点があれば必ず専門家に相談し、納得できるまで確認することが大切です。
5-2 )近隣とのトラブルリスクを把握する
土地活用によって周囲の環境が変わると、近隣住民とのトラブルが発生することもあります。
例えば、駐車場を作った結果、交通量や騒音が増え苦情が寄せられることがあります。また、野立て看板を設置すると、景観問題でクレームが出ることもあります。
一度トラブルが起きると地域での信頼を失ったり、事業の継続に支障が出たりする恐れがあります。良好な関係を保つことは円滑な土地活用に欠かせません。
- 対応の手間(時間と労力)
- 改修や撤去等に費用がかかる
- 事業中止となった場合の初期費用の未回収 など
計画段階で自治体の指導を受けたり必要に応じて説明会を開いたりすることで、後々の大きなトラブルを防ぐことができます。
トラブルになりそうなリスクを事前に予測し、できるだけ近隣への配慮を怠らないことが大切です。
5-3 )税金・維持費を見落とさない
「初期投資ゼロ」や「手間いらず」といわれる土地活用でも、実はランニングコストが発生するケースが少なくありません。
例えば、駐車場経営でも固定資産税や雑草の除去費用、清掃費用がかかります。
太陽光発電の場合も、設備の点検や修理にコストが必要です。
さらに、活用方法によっては、土地の評価額が上がり固定資産税や都市計画税が増えることもあります。
- 税金(固定資産税、都市計画税、住民税、相続税、譲渡税など)
- 管理費用(管理委託費、修理・修繕費、消耗品費、ゴミの処分費など)
- 光熱費(電気、ガス、水道、上下水道料金など)
- 交通費(手続きや業務の移動)
これらの費用を見落とすとせっかくの収益が目減りし、赤字になってしまうことも。
活用を始める前に、毎年かかる費用を具体的に試算しておき、収益とのバランスを必ず確認しましょう。
6 )お金をかけない土地活用を成功させるために
土地活用は、スタートして終わりではありません。長く安定した成果を得るためには、事前の準備とその後の運用が大切です。
ここでは、お金をかけない土地活用を成功させるために特に意識しておきたい3つのポイントを紹介します。リスクを抑えながら着実な成功へとつなげていきましょう。
6-1 )まずは専門家に相談してみよう
土地活用には、法的な規制や税務上の注意点、地域ごとの特性など、個人では判断しにくい要素がたくさんあります。
特に、お金をかけない土地活用の場合でも、「どういった方法が自分の土地に向いているか」「リスクはどこにあるか」を見極めるために専門家のアドバイスが欠かせません。
最近では、不動産会社や土地活用専門業者による無料相談サービスも増えているので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
土地活用の相談先
①土地活用コンサルティング会社
土地活用に関する専門知識を持ち、土地の状況や希望に応じて最適な活用方法を提案してくれる会社です。複数の選択肢を比較しながらアドバイスしてくれるため、初めて土地活用を考える方にとって心強い存在です。また、税務や法律の面でも他の専門家と連携してサポートしてくれる場合もあります。
➁不動産会社(地元密着型)
地域の事情に詳しい不動産会社は、土地の特性や需要を踏まえた活用方法を提案してくれます。特に「駐車場」「貸店舗」「貸地」など、地域のニーズに基づいたアドバイスが得られます。
③市区町村の無料相談窓口(空き家・空き地対策課など)
多くの自治体では空き地や空き家の活用を支援する無料相談窓口があります。税制優遇や補助金の情報、農地の扱いなどについても教えてもらえるため、初めての人にとって心強い存在です。
6-2 )小さな一歩から始めるのが成功のコツ
土地活用というと、大規模な投資や大がかりな工事をイメージしがちですが、お金をかけない方法なら「小さく始める」ことができます。
例えば、最初は駐車場として数台分だけ貸し出してみたり、空き地に小規模な貸倉庫を設置してみたりと、無理のない範囲でスタートするのがポイントです。
最初から大きな収益を狙うのではなく、少しずつ経験を積みながら需要やリスクを見極めていくことが、結果的に失敗を防ぎ、長期的な成功につながります。
6-3 )定期的に土地の活用状況を見直そう
一度土地活用を始めたからといってずっと同じ方法で良いとは限りません。
社会のニーズや周囲の環境は常に変化しており、それに合わせて活用方法も見直す必要があります。
例えば、最初は駐車場として運用していても周辺に大きなショッピングモールができた場合、貸店舗用地に切り替えた方が収益性を高くできるかもしれません。
定期的に活用状況をチェックし、収益や維持費、地域の変化を観察して、必要に応じて改善策を講じましょう。
柔軟に対応していくことで、土地の価値を最大限に活かし続けることができます。
7 )まとめ

土地は「持っているだけ」では税金や管理費といったコストばかりがかかってしまいます。
しかし、無理な投資をしなくても、工夫次第で収益を生み出す方法はたくさんあります。
まずは「自分の土地に合った活用方法を選ぶこと」が大切です。
定期借地権や建設協力金方式など、初期投資を抑えられる方法を活用しつつ、駐車場経営や貸倉庫、太陽光発電といった身近な選択肢も検討していきましょう。
「専門家への相談」「少額で小さく始める」「定期的に見直す」の3つのポイントを活かし、リスクの軽減と大きな失敗を防ぎ、お金のかからない土地活用を成功させてください。
まずは行動から、一歩を踏み出すことが大切です。