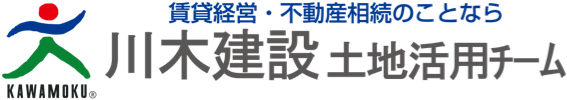【借地借家法】土地活用でオーナーが知っておくべき法律と契約のポイントを解説!
はじめに
空き地を運用する際に借地借家法について知らないと土地が変換されなかったり、思うような土地活用ができなかったりすることがあります。
でも、借地借家法はなんだかわかりにくいと悩んでいませんか?
この記事では、土地活用を考えているオーナーの立場から、借地借家法の基本とその押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、借主の権利や契約期間の考え方、オーナーとしての注意点などを正しく理解し、将来のトラブルを未然に防いだ上で、安心して土地活用を進めることができるようになります。
目次
1-1 )借主保護を目的とした特別法
1-2 )民法との違いと優先順位
1-3 )適用されないケースとその条件
1-4 )借地と借家の違い
2 )借地権の種類と存続期間
2-1 )普通借地権とは
2-2 )定期借地権とは
2-3 )借地権の存続期間とルール
3 )借地契約の更新制度
3-1 )合意更新とは何か
3-2 )請求更新とは?
3-3 )法定更新の仕組み
4 )借地の地代・家賃の変更
4-1 )地代の増額請求と条件
4-2 )減額請求にも対応が必要
4-3 )家賃・地代の適正相場を把握する重要性
5 )建物買取請求権とは
5-1 )借地契約終了時の借主の権利
5-2 )オーナーにとっての負担とリスク
5-3 )建物買取請求を回避する方法
6 )建物の再築とオーナーの対応
6-1 )再築の定義と要件
6-2 )正当事由と承諾拒否の制限
6-3 )事前合意と特約の重要性
7 ) 特約条項の有効性と制限
7-1 )特約の基本と目的
7-2 )無効となる不利な特約とは?
7-3 )有効な特約と記載例
8 )まとめ
1 )借地借家法とは

借地借家法は土地や建物の貸し借りに関する法律で、「借りる人(借主)」を保護することを目的としています。
ここでは、最低限押さえておきたい「借地借家法の基本」をわかりやすく解説します。
1-1 )借主保護を目的とした特別法
「借地借家法」とは、土地や建物を借りて使う人=借主の権利を守るために定められた特別な法律です。
住まいや事業のために不動産を借りている人が、急に立ち退きを迫られたり、極端に不利な条件で契約を結ばされたりすると生活だけではなく命に関わることもあります。
土地の貸し借りでは基本的に土地をもっている貸主(オーナー)の立場が強いため、借主を保護する目的でつくられています。
借地借家法をオーナーの目線で考えたとき、「自由に貸したり、契約を終わらせたりしたい」という意思が制限される場合があることに注意が必要です。
例えば、契約満了後にオーナーが「更新せずに土地を返してほしい」と言っても、借主に引き続き使いたいという希望があり、かつオーナー側に「正当な理由」がなければ、契約は自動的に延長されてしまうことがあります。
オーナーであるあなたが土地活用を始めるうえでは、「借地借家法により借り手が強く保護される」というルールを理解し、それを前提に契約内容を検討することが大切です。
1-2 )民法との違いと優先順位
不動産の賃貸借契約には本来民法が適用されます。しかし、借地借家法はこの民法よりも優先されるルールとして位置づけられています。
両方にルールがある場合には、借地借家法が優先されるということです。
不動産の賃貸借契約には、「民法」と「借地借家法」という2つの法律が関係します。
民法はすべての契約に共通して適用される一般的な法律で、あらゆる契約の基本ルールを定めています。一方、借地借家法は、土地や建物を借りて使う人(借主)を保護するために、特に強いルールを定めた「特別法」です。
①民法が適用される範囲
次のようなケースでは民法のみが適用されます。
- 建物を建てる目的がない土地の貸借(例:青空駐車場、資材置き場など)
- イベントなど短期の「一時使用」の契約
- 家賃が発生しない「使用貸借」契約(無償で貸す場合)
これらのケースでは契約の自由度が高く、民法の一般的なルールに従って貸し借りの条件を設定することができます。
➁借地借家法が適用される範囲
次のようなケースでは、借地借家法が優先的に適用されます。
- 建物を所有する目的で土地を借りる場合(借地)
- 建物を借りて使用する場合(借家)
建物がある(または建てる予定がある)ことが前提となります。この場合、民法のルールよりも借地借家法の規定が優先され、借主の権利をより強く保護します。
民法では「契約期間終了=契約終了」が原則ですが、借地借家法では、契約期間が終了しても自動更新される場合があるため、貸主が一方的に契約を終了させることが難しくなります。
1-3 )適用されないケースとその条件
借地借家法は非常に強い借主保護を行う法律ですがすべての土地貸借に適用されるわけではありません。
以下のようなケースでは適用されないため、オーナーの自由な判断が比較的しやすくなります。
①青空駐車場、資材置き場、太陽光発電
これらの用途では、土地の上に建物を建てないケースがほとんどです。借地借家法は「土地の上に建物を建てて使う」ことを前提としているため、建物がない場合は対象外になります。
➁一時使用(例:イベント利用や短期契約)
展示会やイベントで一時的に土地を貸す場合など、「明らかに一時的」と判断される用途では借主保護の対象外になります。ただし、契約の内容や実態が「実は継続的な利用」であると判断されると、借地借家法の適用対象となる可能性があるため、契約書には「一時使用であること」を明記することが重要です。
③使用貸借(無償で貸す契約)
賃料が発生しない「使用貸借契約」の場合、借地借家法の適用対象とはなりません。たとえば親族に無償で土地を貸している場合などが該当します。
1-4 )借地と借家の違い
借地借家法には、「借地」と「借家」という2つの形態があります。似た意味合いですが「借地」と「借家」では権利や責任の範囲が異なります。違いを正しく理解しておくことが大切です。
①借地=土地の利用権を貸すこと
借地とは、建物を建てる目的で土地を貸す契約のことです。
借主は、土地そのものを購入せずに、一定期間その土地を使用する「権利(借地権)」を得ます。
建物は借主が自ら建てるケースが一般的です。そのため、「土地の所有者(貸主)」と「建物の所有者(借主)」が異なる状態になります。
➁借家=建物の使用権を貸すこと
借家とは、すでに建っている建物を借りる契約を指します。
マンションやアパート、一戸建ての賃貸住宅がこれにあたります。
この場合、貸す対象は土地ではなく「建物そのもの」で、土地のことは基本的に契約の対象外です。
③適用される規定も異なる
借地と借家では、借りる対象が「土地」か「建物」か、という違いがあるためそれぞれに適用される法的ルールも異なります。
契約期間の定め方や更新、解約の条件、契約終了時の処理(建物買取請求など)も異なるため、自分がどちらの契約形態に該当するかを正確に把握することが重要です。
2 )借地権の種類と存続期間

借地借家法における「借地権」には、主に2つの種類があります。
1つは更新が前提となる「普通借地権」、もう1つは契約期間満了で確実に終了する「定期借地権」です。
土地活用をする上では、どちらの借地権を利用するかによって、将来的な資産の運用計画が大きく変わってきます。
2-1 )普通借地権とは
普通借地権は、借地借家法における基本的な借地権で、長期的な土地の貸し出しを前提とした契約形態です。
①契約は更新され続けるのが原則
契約期間が終了しても、借主(借地人)からの更新請求があれば、貸主(オーナー)側に「正当な理由がない限り、契約の終了を拒むことができません。オーナーの一方的な都合で契約を打ち切ることは難しい仕組みになっています。
オーナー側としては一度土地を貸すと、長期間にわたって返ってこない可能性もあるという点には注意が必要です。土地の活用方法を見直したい時期になっても、借主が契約更新を希望すれば基本的には継続されます。
➁長期安定した利用に向いている
借主にとっては長期的な土地利用が保障されるというメリットがあります。例えば住宅用地や事業拠点としての使用には適しています。
オーナー側としては、自由に土地を使い戻すことが難しくなるため、「将来的に売却や再開発を考えている」といったケースには不向きです。
2-2 )定期借地権とは
定期借地権は、契約期間の終了をもって確実に土地が返ってくる仕組みです。契約時に「更新しないこと」を明確に取り決めておくことで確実に土地が返還されます。
①契約満了で終了、更新なし
定期借地契約では契約期間満了と同時に借地権が終了し、借主に更新請求権はありません。借主が引き続き土地を使いたいと望んでもオーナー側が拒否できるため、将来的な土地の利用計画を立てやすくなるという点が魅力です。
➁用途に応じた3種類がある
定期借地権には、用途や契約内容に応じて以下の3つのタイプがあります。
- 一般定期借地権(50年以上)
- 事業用定期借地権(10~50年)
- 建物譲渡特約付借地権
住宅などの長期利用を前提とした契約。建物の買取請求は不可。
店舗や工場など、事業目的に利用される土地。住宅用途には使えません。
契約終了時に建物をオーナーに譲渡する条件付き。期間は30年以上。
これらを活用することで、一定期間だけ土地を貸し、将来は自由に使える状態に戻したいというオーナーのニーズに対応できます。
2-3 )借地権の存続期間とルール
借地契約を結ぶ際にとても重要なのが、「契約期間の長さ」です。これは法律である程度のルールが定められており、オーナーの意向だけで自由に短縮することはできません。
①普通借地権の期間は30年が基本
普通借地権では、契約で期間を定めた場合でも、最初の契約期間は最低30年とされています。
「15年だけ貸したい」と思って契約を結んでも、その契約は無効とされ、自動的に30年とみなされる点に注意が必要です。
更新する場合、1回目の更新は最低20年、それ以降は10年が必要です。契約の度にある程度の長期間が保障されることになります。
①定期借地権は自由度が高い
一方、定期借地権では、契約によって自由に期間を設定することができます。事業用の場合は10年以上、一般住宅用なら50年以上という最低ラインはあるものの、更新がないため、その期間終了後には確実に返還されます。
③期間未定でも30年とみなされる
契約書に「契約期間」の記載がない場合でも、法律上は自動的に30年とみなされます。これは借主保護の観点から、最低限の使用期間を保障するためのルールです。
3 )借地契約の更新制度
借地契約は契約期間が終わっても借主に契約の継続を強く保護される権利があり、オーナー側が一方的に契約を終わらせるのは困難です。
更新の方法には主に3つあり、それぞれルールが異なります。将来の土地の活用計画に支障を出さないためにも、契約の更新制度について正しく理解しておく必要があります。
3-1 )合意更新とは何か
合意更新とは、契約期間が満了する際に、貸主(オーナー)と借主が双方の合意によって契約期間を延長する方法です。
①契約満了前に話し合って更新
「契約期間30年」の借地契約が満了する前に、オーナーと借主が話し合い、「さらに20年延長しよう」と合意する場合がこれにあたります。両者が納得したうえで更新されるため、最もトラブルが少ない更新方法です。
➁書面での契約更新が重要
合意更新の場合は新たに更新契約書を作成することが大切です。口頭だけの合意では証拠が残らず、後々トラブルのもとになりかねません。更新後の契約期間や条件、地代(家賃)などを明記しておくことで、トラブルを未然に防げます。
3-2 )請求更新とは?
請求更新とは、契約満了時に借主から「更新したい」と申し出ることで契約が継続される制度です。借主が更新を望めば、オーナーは原則としてこれを拒否できません。
①正当事由がなければ断れない
オーナーが請求更新を拒否するためには、「正当事由」が必要になります。これは非常にハードルが高く、単に「土地を返してほしい」や「今後別の活用をしたい」といった理由だけでは認められません。
➁正当事由として認められる可能性のある例
- オーナーが自らその土地を使用する必要がある
- 借主に契約違反や地代滞納がある
- 多額の立退料を支払うことでバランスが取れる
実質的にはオーナー側が不利になりやすい更新方式であり、「貸したら基本的には戻ってこない」という感覚で捉えておくべきです。
3-3 )法定更新の仕組み
契約期間が終了しても、更新の合意や借主からの請求がないまま土地の使用が続けられた場合には、「法定更新」とみなされ、契約が自動的に更新されたと扱われます。
①黙って使い続けるだけで更新される
オーナーが「更新しない」と伝えずに、借主がそのまま土地を使い続けていた場合、裁判所などは「黙示の合意(無言の了解)があった」と判断します。
これを「法定更新」といい、更新契約書がなくても借地契約が続いてしまうことになります。
➁正式に終了したいなら事前通知が必要
自動更新を防ぐためには、契約満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨を文書で通知する必要があります。
期限を過ぎると「更新の合意があった」とみなされてしまうため、スケジュール管理と文書による手続きが極めて重要です。
4 )借地の地代・家賃の変更
借地契約では、契約時に取り決めた地代(家賃)が将来的にそのまま維持されるとは限りません。
契約が長期にわたることが多い借地契約では、経済状況や地価の変動、税制の変更など、さまざまな要因で地代を見直す必要が出てきます。
この章では、オーナーが地代の増額や借主からの減額請求にどのように対応すべきか、またトラブルを防ぐための相場の把握について解説します。
4-1 )地代の増額請求と条件
オーナーが地代を上げたいと考える場面は少なくありません。たとえば、次のような場合です。
- 周辺の地価が大幅に上がった
- 固定資産税などの負担が増えた
- インフレにより物価全体が上昇した
これらを理由として、借主に対して地代の増額請求をすることが可能です。
①増額請求には「合理的な理由」が必要
「収益を上げたいから」という理由では認められません。法的には「地代が不相当に低い場合」に限って契約にかかわらず増額請求が可能とされています。
➁借主が応じない場合は調停や訴訟へ
借主が増額に同意しない場合は、話し合いがつかないまま調停や訴訟に発展する可能性もあります。そのため、根拠となる資料(周辺相場のデータ、固定資産税の通知書など)を用意することが必要です。
請求後すぐに新しい地代が適用されるわけではなく、合意に達するまでは旧地代の支払いが続きます。
4-2 )減額請求にも対応が必要
- 周辺の地価が大きく下がった
- 土地の利用状況が変わって収益が出なくなった
- 建物が老朽化して利用価値が下がった
①正当な理由があれば減額に応じる必要がある
借地借家法では、借主からの減額請求にも法的根拠があります。こちらも「地代が不相当に高い」と判断される場合に限り、契約に関係なく見直しが可能です。
➁一方的な拒否はリスクになる
オーナーが「今まで通り払ってくれ」と一方的に突っぱねてしまうと、関係がこじれて調停や訴訟に発展するリスクがあります。最悪の場合、借主が地代の支払いを一時的に止めるような事態になることも考えられます。
このような場合は冷静に理由を確認し、根拠資料の提示を求めるとともに、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
4-3 )家賃・地代の適正相場を把握する重要性
オーナーとしては、日頃から現在の地代が「高すぎず・安すぎず」であるかを把握しておくことが大切です。トラブルを避けるためにも次の3つのポイントを押さえておきましょう。
①相場に合わない契約はトラブルのもと
たとえば、周辺相場より明らかに高額な地代を請求し続ければ借主から不満が出ますし、逆に安すぎる場合には収益機会を逃していることになります。いずれも不健全な状態です。
➁定期的な相場調査をしておく
不動産会社に相談することやインターネット上の賃貸相場サイト、近隣地域の公示地価などを活用すれば、おおよその目安を把握することは可能です。
また、固定資産税の評価額や税制の変更なども見直しの判断材料となります。年に一度程度は資料を確認する習慣をつけておきましょう。
③調整はオーナー主導で
トラブルを避けるためにも、いざ請求が来てから慌てるのではなく、オーナー側が定期的に見直しのタイミングをつくることが望ましいです。あらかじめ契約書に「5年ごとに見直し」などの条項を設けることも有効です。
5 )建物買取請求権とは
借地契約が終了しても、借主がその土地に建物を残したまま退去しないというケースは少なくありません。そのような場合、オーナーが直面するのが「建物買取請求権」です。
「建物買取請求権」は、借主がオーナーに対して建物を買い取るよう請求できる権利であり、借地借家法によって認められています。
借主保護の目的で設けられた制度ではありますが、土地オーナーにとっては予想外の出費や交渉リスクとなることもあります。
この章では、建物買取請求権の基本から回避策まで、オーナーに必要なポイントを解説します。
5-1 )借地契約終了時の借主の権利
借地契約が満了し、借主に退去してもらいたい場合でも、その土地に建物が存在していれば、借主は「建物を買い取ってください」とオーナーに請求できる権利を持っています。これが建物買取請求権です。
①建物が存在していることが前提
この権利が発生するのは、「借地上に借主が所有する建物が存在している場合」に限られます。例えば、借地契約終了後に借主がまだ建物を取り壊していない、あるいは使っていた建物をそのまま残している場合などが該当します。
➁建物の評価と買い取り金額
オーナー側が買い取る場合、その金額は「建物の時価(市場価値)」が目安になります。新築や築浅であれば高額になりますし、老朽化していれば低くなります。評価は不動産鑑定士や第三者の専門家に依頼することが一般的です。
5-2 )オーナーにとっての負担とリスク
建物買取請求権は、借主の保護を目的とした制度ですが、オーナーにとっては以下のような思わぬ負担やリスクにつながることがあります。
①建物付きで土地を取り戻すことになる
土地を返してもらえると思っていたのに、「建物が残った状態で戻ってくる」ことになります。空き地ではなく不要な建物が残ったまま返還されることで、次の土地活用に支障が出る可能性があります。
➁買い取り費用の負担
築年数や建物の構造によっては、数百万円単位の支払いが発生するケースもあります。返還後の資金計画にも影響が出る可能性があるため、買取を想定しておく必要があります。
③交渉トラブルに発展する可能性
オーナーが「買い取りたくない」と拒否した場合でも、法的には借主の権利が優先されます。調停や訴訟に発展するケースもあり、対応には冷静かつ専門的な判断が求められます。
5-3 )建物買取請求を回避する方法
建物買取請求権でのトラブルを未然に防ぐためには、契約時点での工夫が重要です。以下のような方法で、建物買取請求権の発生を制限することが可能です。
①契約書に「特約」を盛り込んでも回避できない
借地契約終了時に借主から建物の買取を請求される「建物買取請求権」は、借地借家法に基づく強行規定であり、通常の(普通)借地契約においては特約で排除することはできません。つまり、契約書に「建物は買い取らない」と記載していても、その特約は無効とされるため、オーナーは請求に応じなければならない可能性があります。
➁定期借地権の活用
建物買取請求権のリスクを避ける有効な手段としては、「定期借地契約」を活用することがもっとも堅実です。定期借地契約では期間の延長なしに建物も取り壊し、更地にして返すことを前提とした契約になります。これにより不要な建物を残されたり買い取ることを防ぐことができます。
③買取請求権が適用されないケース
買取請求権はどんな状況でも適用されるわけではありません。適用されないケースも理解し不要な買取を回避することも大切です。
買取請求権が認められるには次の要件を満たす必要があります。
- 借地契約の期間満了によって契約が終了する場合
- 債務不履行や契約違反がない場合
- 借地上に借主が建てた建物が存在していること(第三者が建てた建物でないこと)
- プレハブや仮設物などのように簡易的で取り外し可能な構造物でないこと
- 建物が滅失していたり、既に取り壊されていないこと(使える状態であること)
このような場合は買取請求権を回避できる可能性がありますので、契約を終了する際に確認しておきましょう。
6 )建物の再築とオーナーの対応

借地契約が続いている間に古くなった建物を借主が建て替えたい(再築したい)と希望するケースは多くあります。しかし、再築を行うにはオーナーである貸主の承諾が原則必要です。
借地借家法では借主保護の観点から、オーナー側が自由に再築を拒否できないというルールも存在します。
ここでは、建物の再築に関する基本的な仕組みから、オーナーが注意すべきポイントや契約時の工夫までをわかりやすく解説します。
6-1 )再築の定義と要件
「再築」とは、一般的に建物の建て替えを指します。一部の改築や大規模修繕も含まれる場合があります。例えば、増築や構造の一部を変更するような工事も内容によっては再築とみなされることがあります。
借地契約のなかで、建物を再築するには貸主(オーナー)の事前の承諾が必要とされるのが一般的です。これは、勝手な再築によって土地の利用目的や契約内容が大きく変わる可能性があるためです。
ただし、オーナー側が「承諾しない」と主張しても、それが法的に認められないケースもあります。
6-2 )正当事由と承諾拒否の制限
借地借家法では、借主が再築を希望した際に、貸主側が一方的に断ることを原則として認めていません。つまり、オーナーには「正当な理由」がなければ、再築の承諾を拒否できないのです。
以下のようなケースが「正当な理由」として認められる可能性があります。
- 再築によって周辺に悪影響が出るおそれがある(騒音・安全性など)
- 建物の用途が契約内容に反する(例:住宅用契約なのに店舗へ変更)
- オーナーが近々その土地を自分で使用する予定がある
単に「承諾したくない」「今後の活用に支障が出そう」という主観的な理由だけでは認められないことが多いです。
実際には、借主が再築の許可を求めたがオーナーが理由なく拒否したことで調停に発展することもあります。こうした事態を避けるためにも、契約時に「再築のルール」を明確にしておくことが大切です。
6-3 )事前合意と特約の重要性
建物の再築をめぐるトラブルを避けるには、契約段階での明確な取り決めが重要です。オーナーが将来の土地活用を考える上でも、再築に関する自由度をコントロールすることはリスク管理のひとつになります。
例えば、以下のような条文を借地契約に盛り込むことでオーナーの意図を明確にできます。
- 建物の再築には書面による貸主の承諾を要する
- 用途変更や増築を含む改築は、貸主の事前承諾がない限り禁止する
ただし、あまりにも借主に不利すぎる条件(たとえば再築を一切禁止するなど)は、裁判で無効とされる可能性があるため注意が必要です。
7 )特約条項の有効性と制限

借地契約を結ぶ際、「特約」という項目を契約書に盛り込むことがあります。これは、借主・貸主の双方が自由に決めた追加ルールのことですが、なんでも自由に決めて良いわけではありません。
借地借家法には、借主保護のために特約の有効性を制限する規定があるため、オーナーとしては「有効な特約」と「無効になる可能性が高い特約」の違いを理解しておくことが重要です。
7-1 )特約の基本と目的
「特約」とは、契約書に記載される、基本条項以外の特別な取り決めのことです。法律の範囲内で、借主と貸主が話し合って合意した内容が反映されます。
①特約の目的
特約を使うことで、以下のようなオーナーの意向を契約に反映できます。
- 途中解約の条件を明確にしたい
- 建物の用途や再築について制限したい
- その他法律範囲外の取り決めやルールの確認
借地借家法の原則だけでは対応しきれない個別事情に対応する手段として使われます。
➁特約は「合意」が前提
特約は一方的にオーナーが決めるのではなく、借主の合意があることが前提です。形式的に署名があっても、内容があまりに不利な場合は後述のように「無効」とされることがあります。
7-2 )無効となる不利な特約とは?
借地借家法では、借主に一方的に不利益となる特約は無効とされています。これは、借主が弱い立場にあることを前提とした保護の考え方です。
①無効となる特約の例
- 借主は一切再築をしてはならない
- 契約期間中であっても、貸主の判断で契約解除できる
- 更新を認めず、立ち退きに応じない場合は違約金○○万円
このように、借主に対して一方的・過度な制限を課す内容は、たとえ契約書に書いてあっても裁判などで無効と判断されることがあります。
➁借主の弱者保護が優先される
オーナーにとっては「念のために条文を盛り込んだ」という意図でも、それが借地借家法の趣旨に反していれば意味がない、あるいはトラブルの火種になる可能性もあります。
7-3 )有効な特約と記載例
借主に不利になる特約がすべて特約が無効になるわけではありません。借地借家法上でも有効とされる特約があり、オーナーがリスク管理するうえで有効活用できる場面も多くあります。
①有効な特約の代表例
- 定期借地契約の終了条項
- 建物買取請求権の排除条項(定期借地のみ)
- 再築・用途変更の承諾制限
→「この契約は更新せず、期間満了により終了する」
→「期間満了後、借主は建物買取請求を行わないものとする」
→「借主が建物を再築・増改築する場合は、貸主の書面による承諾を要する」
➁記載方法と注意点
特約は曖昧な表現だとトラブルのもとになります。以下の点に注意しましょう。
- 条文は具体的・明確に書く(例:「期間終了後は立ち退く」など)
- 契約書内で見落とされないよう、見出し・目立つ形で明記する
- 書面での合意(署名・捺印)を必ず取得する
契約書作成時には出来るだけ弁護士など専門家のチェックを受けておくと安心です。
8 )まとめ
借地借家法は、土地や建物を貸すオーナーにとって必ず理解しておくべき法律です。特に、契約の終了や更新、家賃の改定といった実務に深く関わる内容が多く含まれており、法律を無視した運用はトラブルの原因になります。
オーナーとして適切な契約書を作成し、相手との合意を法的に正しく進めるためにも、借地借家法の基礎をしっかりと押さえておくことが土地活用の成功につながります。
今回の記事を参考に長期的で有効的な土地の運用計画に役立ててください。